皆さんはペンキの使用期限を気にしたことがありますか?
医薬品や化粧品などと同じで、実はペンキにも使用期限があるんですよ。
「ペンキを購入したけど余ってしまった」「古いペンキが出てきたけど、まだ使える?」
など、ペンキの使用期限を知らないと、使えるのか使えないのかの判断に迷うと思います。
ペンキを購入する際も、使用期限に応じて選ぶ容量が変わるのではないでしょうか。大きめの容量のペンキを買っておいて少しずつ使いたい、という人もいるはずです。
使用期限ぎりぎりまでペンキの状態を保つには、保管状態も大きく影響します。
このコラムでは、ペンキの使用期限はどれくらいなのか、具体例を挙げながら紹介していきます。適切な保管方法や古いペンキの使用可否の判断基準なども参考にしてください。
一般的なペンキの使用期限について
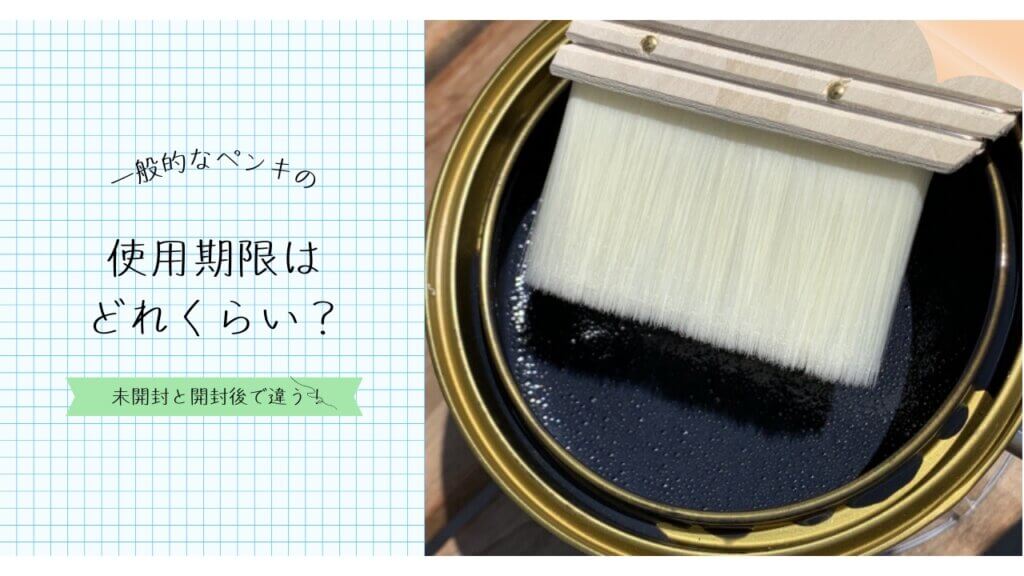
ペンキの使用期限とは、ペンキの品質が保てると保証された期限のことです。
つまり、使用期限を過ぎると、ペンキ本来の性能が発揮できなくなる可能性があるということです。
一般的には、家庭用ペンキの使用期限は未開封の状態で製造から1年程度と考えられています。。
また、多くの塗料メーカーでは、「開封後はなるべく早く使用すること」と表示しています。
しかし、これはあくまでも目安であり、明確に定義されたものではありません。
保管状態が良ければ、1年以上持つケースもあるようです。保存状態では未使用で製造日から3〜5年としているところもあります
仮に1年程度を使用期限の目安とすると、意外と短い印象を受ける方は多いのではないでしょうか。長期間の保存で変質する可能性があるため、1年以内に使用する予定のないペンキをまとめ買いする、という方法はあまりおすすめできません。
ペンキの種類や製品による使用期限の違い
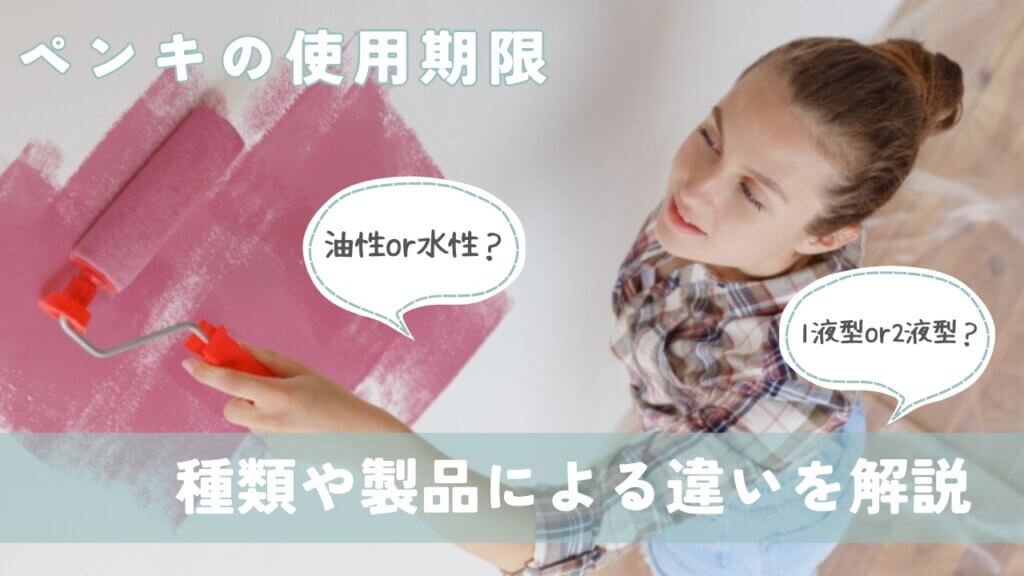
ここでは、具体例を挙げて、ペンキの使用期限の違いを解説していきます。
1液型と2液型の違い
外壁塗装の際に見かけるペンキの分類の一つに、1液型と2液型があります。1液型は、すでに硬化剤が含まれている塗料のことで、開封後すぐに塗装できるのが特徴です。
一方、2液型は、主剤と硬化剤が分けられている塗料で、使用直前に混ぜる必要があります。
1液型は硬化剤の影響で少しずつ固まるため、使用期限が半年から1年とやや短めです。2液型は硬化剤が含まれないため、1液型よりも長く保存できます。
とはいえ、どちらも長期間保存できるものではないため、早めの使用が推奨されています。
水性ペンキと油性ペンキの違い

油性ペンキの方が水性ペンキよりも使用期限が長いイメージがあるかもしれません。
しかし、水性ペンキを扱う一部のメーカーでは、未開封であれば3〜5年保管できるとしており、水性ペンキでも一般的な使用期限より長く保管できる場合もあります。
ただし、開封後については、水を入れた水性ペンキは腐りやすくなっています。そのため、使いかけの水性ペンキは保存ができないと考えた方が良いです。
油性ペンキについても、国内の塗料メーカーの多くが「開封後・使用後は半年以内に使い切るようにすること」と表示しています。
機能性塗料やオーガニックペンキは使用期限が短い

機能性塗料とは、ペンキ本来の機能(美観向上や塗布面の保護)以外に、特別な機能が付加された塗料を指します。例えば、遮熱効果や防音・吸音効果、錆止め効果、防汚効果などがあるペンキです。
これらの機能性塗料は、時間経過に伴う品質の変化により、十分な性能が発揮できなくなる恐れがあります。そのため、一般的なペンキよりも使用期限が短めに設定されています。
具体例を挙げますと、
・天然物質(イカ墨)を使用した抗菌性・消臭性のあるペンキ⇒未開封で半年
・ロケットにも使用されている断熱塗料ガイナ⇒未開封で3ヶ月
などが挙げられます。
オーガニックペンキは、保存性を高めるための防腐剤が含まれていないため、通常のペンキよりも腐りやすいです。例えば、エコスの使用期限は、未開封の状態で1年以内。開封後は早めの使用が推奨されます。
ペンキを使用期限まで持たせるための適切な保管方法

ペンキの種類や製品、開封・未開封を問わず、直射日光の当たらない涼しい場所に保管するのが基本です。極端な高温や低温は避けること、特に凍結が起こらないように注意しましょう。
上記を踏まえ、ペンキの適切な保管方法をまとめます。
ペンキに空気が触れないようにする
開封済みの場合、ペンキに空気が触れるのは厳禁です。ペンキが空気に晒されると硬化し始めるので、密閉できる容器に入れて保管するようにしてください。ペンキを保管する容器は、ペンキの残量に比べて大きすぎないサイズがベターです。容器が大きすぎると、空気が多い状態になるので、ペンキの乾燥を進める原因になります。
もし、容器に対して残ったペンキが少なくなってしまったら、別の容器に移し替えましょう。
容器にペンキが付いたまま保管しない
缶タイプの場合、ペンキがふちに付いた状態でフタを閉めると、わずかに隙間が生じる可能性があります。この隙間から空気が入り、ペンキが乾燥してしまうことがあるのです。
隙間は空いていなくとも、漏れ出たペンキが固まり、次の塗装時にフタが開けられないトラブルが発生することもあります。
パウチタイプのペンキも同様で、フタのスクリュー部分にペンキが付いていると固まって開かなくなります。
次の塗装時にスムーズに開けるためにも、容器にペンキが付いたまま保管しないよう注意が必要です。缶のふちに付着したペンキを綺麗に拭き取り、フタをしっかり閉めて保管しましょう。
水性ペンキは不純物の混入に注意する

ペットボトルなどでも保管できますが、清潔かつ適切なサイズの容器を選ぶことが大切です。
塗装時は、ペンキの容器に直接塗装用具(刷毛やローラー)を付けるのを避けてください。塗装用具や塗装面に付いた不純物が混入した場合、腐敗の原因になります。
油性ペンキはペイントうすめ液を入れる
油性ペンキは、保存中に容器内で固まりやすいです。硬化を防ぐために、残ったペンキの上にペイントうすめ液を少量入れてから保管します。ペイントうすめ液がペンキのフタになってくれるので、乾燥による硬化を防げます。
また、油性塗料の中には、火気の近くなど高温の場所に置いておくと、膨張して破裂する恐れがあるものもあります。
安全のためにも、高温多湿を避けて保管しましょう。
まだ使える?古いペンキの使用可否の判断基準
使用期限が分からない古いペンキや、製造から1年以上経過しているペンキは、「使用できるか、できないか」の判断に迷いますよね。 皆さんの自宅にある古いペンキは、まだ使えるのでしょうか。判断基準を以下にまとめます。攪拌(かくはん)できるかどうか
ペンキの使用可否の判断基準の一つが、攪拌(かくはん)できるかどうかです。攪拌とは、ペンキをかき混ぜて塗装できる状態にすることをいいます。攪拌が不十分だと、ペンキの成分が不均一な状態なため、塗装後に色ムラができたり隠ぺい力が低下して下地透けが起きたりします。
ペンキが硬化してしまい攪拌できない場合は、使用はおすすめできません。
ペンキがゲル状になっていないか

ペンキのゲル化とは、ペンキが液状ではなく固形、特にゼリー状やプリン状になる現象です。
ペンキがゲル化する原因にはいくつか考えられます。
・ペンキに含まれる樹脂や硬化剤の使用期限切れ
・ペンキの成分を溶かす「溶剤」が揮発した
・2液型ペンキの混合後、ポットライフ(可使時間)が過ぎて硬化した
・ペンキの容器に水分が混入した
など、さまざまな原因でゲル状になります。
ゲル化しているのがペンキの一部分であれば、希釈して復活させられる場合があります。
油性ペンキなら「ペイントうすめ液」を、水性ペンキなら「水」を使って希釈し、攪拌してみましょう。
完全に固形化して攪拌できない場合は、希釈しても復活させられません。
腐敗臭がしないかどうか
主に水性ペンキの使用期限が切れて劣化が進むと、開封時に腐敗臭がすることがあります。これは、ペンキに含まれる水にバクテリアなどの細菌が繁殖するのが原因で、アンモニアや硫化水素などの臭いを発して起きる現象です。
水性ペンキを長期保存している場合や水で希釈したものを保存している場合などに起こります。
また、防腐剤が含まれていないペンキや、防腐剤が含まれていても効果が低減してしまったペンキなどで生じやすいです。
腐敗したペンキは使用できないので、ただちに処分しましょう。
まとめ|ペンキの使用期限は種類や保管方法に影響されます
家庭用ペンキの使用期限は未開封の状態で製造から1年程度、開封後はなるべく早く使用した方が良いというのが一般的な見解です。ペンキの使用期限が分からない時に、一つの目安としてください。
コラム内で解説したように、ペンキの使用期限は種類や保管方法に影響を受けます。
未開封の状態で製造から1年程度、というのはあくまでも参考なので、メーカーが発表している情報があればそちらを優先しましょう。
使用期限いっぱいまで持たせるためにも、正しい方法で保管してくださいね!

WEBライター 原野 光佳(はらの るか)
WEBライターとして、さまざまなジャンルの記事を執筆しています。インテリアデザインやおしゃれな家具・雑貨、色の持つ効果などに関して勉強中です。化粧品や食品などもオーガニックを好んでおり、ユーザー目線でオーガニックペイントの魅力を伝えていきます!

